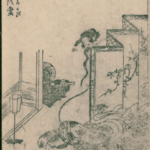経済先行、政治後追いで統治が進んだ江戸の蝦夷地
蔦重をめぐる人物とキーワード㉛
■支配強化の一因となった外圧
江戸幕府が開かれた頃、中央政権にとって蝦夷地(えぞち/主に北海道島)は、近代国家のような明確な国境線が未確立の状況下にあった。この地域は中国、朝鮮、琉球と並び「四つの口」として外交・貿易統制の対象とされたが、蝦夷地には他の三地域と異なり政府機構が存在しなかった。
幕府は、蝦夷地の統治を直接は行わず、北海道島南部に勢力を持つ松前藩に対し、現地の人々との交渉を担当させるという形で間接的な支配体制を展開した。1789年(寛政元年)には、松前藩とアイヌの間でクナシリ・メナシの戦いが起こり、その結果として松前藩の支配力が強化された。このような間接統治の体制下で、蝦夷地では政治的統合に先行して、経済的な統合が進行していくことになる。
日本が蝦夷地との交流を盛んにした結果、日本の商品が大量に蝦夷地に流入し、アイヌ社会の経済的自立は徐々に失われていったとされる。
アイヌの人々の生業は、日本市場で求められる動物性油や皮革、熊の胆、オットセイなどの薬材といった特定品目の採取に次第に専業化した。日本人との交易を前提とする社会へ変容していったのである。市場原理による、現地の社会構造の組み替えが進んだ。
18世紀後半以降、蝦夷地は地政学的な緊張に直面する。ロシアが毛皮貿易を目的としてオホーツク海沿岸へ進出し、通商を要求してきたのだ。にわかに蝦夷地は国防上の要衝と化し、境界線の曖昧さが問題となった。
ロシアが蝦夷地を襲撃するまでに至ると、幕府は、この危機的状況に対応するため、蝦夷地防備を強化する決意を固め、伊能忠敬(いのうただたか)や間宮林蔵(まみやりんぞう)らを派遣した。現地の探索・測量を展開し、国後島(くなしりとう)や択捉島(えとろふとう)への調査を進め、これらの地域における行政的な管理体制を強化していった。
こうした国際的な緊張の高まりを受け、幕府は従来の松前藩による間接統治から方針を転換し、1807(文化4)年に蝦夷地の幕領化を断行した。これにより、北海道島全域が幕府の直接支配下に組み込まれ、長年にわたって経済統合が先行していた蝦夷地において、ようやく政治的な統合が実現した。
この政治的統合により、幕府は蝦夷地に対する行政権を直接行使し、国防体制の整備と資源開発の統制を本格化させることとなった。
政治的統合の後、国境の確定は国際的な交渉によって進められた。1855(安政2)年に幕府とロシアの間で結ばれた日露通好条約により、択捉島とウルップ島の間が両国の境界として確認された。樺太(サハリン)は両国民の雑居地とされたものの、1875(明治8)年の樺太・千島交換条約によって最終的な国境が画定した。
これにより、江戸時代を通じて続いた「経済先行・政治後追い」という独特な統治形態は終焉を迎え、明治政府による本格的な北海道開拓使の設置(1869年)と屯田兵制度の導入によって、近代国家としての直接的な領土統治へと転換していった。
つまり、江戸時代の蝦夷地統治は当初の間接的な統治委託から始
- 1
- 2